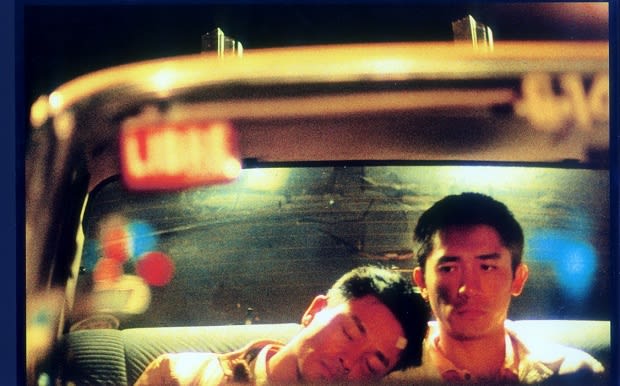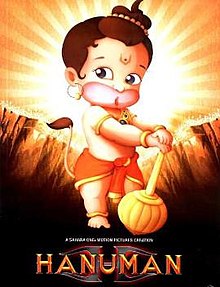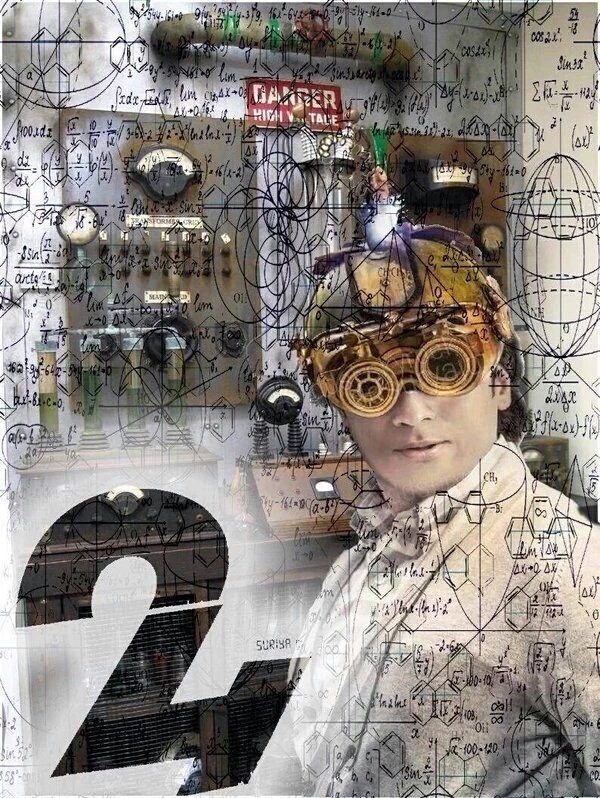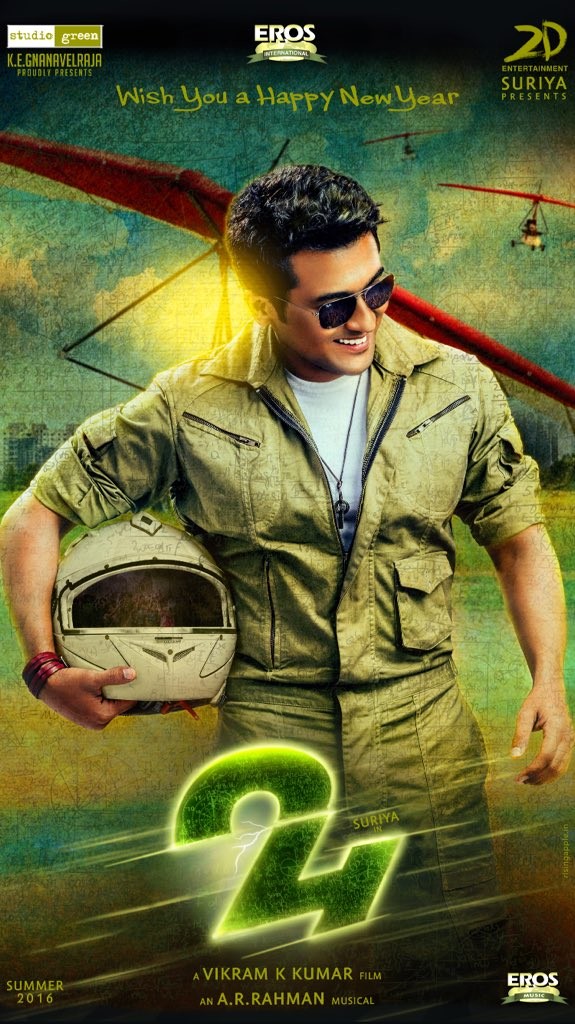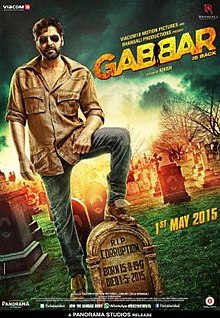賈樟柯(ジャ・ジャンクー)監督の新作『山河ノスタルジア』が、4月23日(土)より公開されます。 昨年の東京フィルメックスで上映されて以降公開が待たれていた作品で、これまでのジャ・ジャンクー監督作品とはひと味違った、新しい地平が切り開かれている意欲作です。まずは基本データをどうぞ。
『山河ノスタルジア』 公式サイト
![]()
(C)Bandai Visual,Bitters End, Office Kitano
2015年/中国=日本=フランス/125分/原題:山河故人
監督:賈樟柯(ジャ・ジャンクー)
主演:趙涛(チャオ・タオ)、張譯(チャン・イー)、梁景東(リャン・ジンドン)、董子健(ドン・ズージェン)、張艾嘉(シルヴィア・チャン)
配給・宣伝:ビターズ・エンド
※4月23日(土)より Bunkamuraル・シネマほか全国順次ロードショー
![]()
(C)Bandai Visual,Bitters End, Office Kitano
主人公は、山西省汾陽(フェンヤン)に住むタオ(チャオ・タオ)。1999年、小学校教師をしていたタオには、2人の男友達がいました。どちらも幼馴染みである、炭鉱労働者のリャンズー(リャン・ジンドン)と実業家のジンシェン(チャン・イー)です。リャンズーは秘かにタオに思いを寄せ、ジンシェンはあからさまにアタックをしますが、タオは態度をはっきりさせません。彼女にとっては、3人で仲良くつるんでいるいまの時間が大切なのでした。そんな中でリャンズーの炭鉱はジンシェンに買収され、ジンシェンは彼を追い出してしまいます。結局タオもジンシェンを受け入れ、二人は結婚し子供をもうけることに。その子は金銭欲の強いジンシェンにより、「ダオラー(ドル)」と名付けられました。
![]()
(C)Bandai Visual,Bitters End, Office Kitano
その15年後、2014年。河北省の炭鉱で働いていてリャンズーは体を壊し、妻や幼い子供と共に汾陽に戻って来ます。その頃タオはジンシェンと離婚し、女性実業家としての地歩を築いていました。別れた夫ジンシェンは幼い息子と共に上海に移り、今では再婚もしています。ジンシェンの仕事も順調で、息子のダオラーを上海の国際学校に通わせるなど、羽振りのよさも昔のまま。タオの父が急逝した時、汾陽に一人帰ってきたダオラーは、タオのことを「マミー」と呼ぶのでした。自分と息子の間の距離の広がりを感じたタオは、あえて鈍行列車で息子を上海まで送っていきます。その時タオが聞き、またダオラーに聞かせた曲は、葉蒨文(サリー・イェ/サリー・イップ)の「珍重」でした。
![]()
(C)Bandai Visual,Bitters End, Office Kitano
そして、さらに11年が経った2025年。ジンシェンは息子ダオラー(ドン・ズージェン)と共にオーストラリアに移住していました。19才になったダオラーは英語にはまったく不自由しないものの、中国語がきちんと話せないため、父との意思疎通もままなりません。ダオラーは中国語のクラスに通い、そこで教師のミア(シルヴィア・チャン)と出会います。ダオラーは、親子以上に年の差があるミアに引かれていき、またミアも、ダオラーが彼女に父との通訳を頼んだことで、この青年の孤独と焦燥感を理解し、徐々に彼に心を寄せていくのでした。そのミアがダオラーに聞かせた曲もサリー・イェの「珍重」で、その曲はダオラーにノスタルジアを呼び起こします。その頃汾陽に暮らすタオは...。
![]()
(C)Bandai Visual,Bitters End, Office Kitano
物語は、過去・現在・未来にまたがり、人の生が描く軌跡を丁寧に追って行きます。友情、男女の愛、親子愛など、様々な形の人と人との結びつきが描かれ、それが崩壊していく様もまた、冷徹な眼差しで見据えられ描かれていきます。本作でジャ・ジャンクー監督は初めて未来を描きましたが、26年という人の生き様の延長線上にあるのが未来だ、ということを観客に教えてくれているかのようです。ただ、未来編では、オーストラリアに渡ったジンシェンの人生ががらりと変わったものになっているなど、中国と中国人の未来を予見したような描写も見て取れます。このあたり、ジャ・ジャンクー監督も一歩踏み込んだというか、新しい世界を描く冒険に踏み出した感があります。
![]()
(C)Bandai Visual,Bitters End, Office Kitano
26年というへだたりを一番上手に体現しているのは、やはりジャ・ジャンクー監督のミューズ、チャオ・タオでしょう。外見の変化だけでなく、1999年の20代では声のピッチを上げ、体の動きも軽やかに表現し、2014年のアラフォー期は自信と貫禄を身にまとってみせ、そして、老境の入り口にさしかかった2025年では、20代と同じ曲を踊っても体の動きぶりを変えるなど、細かく演じ分けています。その彼女に寄り添って時代性を伝えるのが、上で述べたサリー・イェ(北京語読み)/サリー・イップ(広東語読み)の歌です。台湾生まれでカナダ育ちのサリーの歌は、1987年に「甜言蜜語」がヒットし、その後「祝福」(1988)、「珍重」(1990)とヒットが続くのですが、いずれも広東語曲でした。そして1991年には、「瀟灑走一回」という北京語の大ヒット曲が生まれます。ジャ・ジャンクー監督は以前の作品『プラットホーム』(2000)で「瀟灑走一回」を使っていたと思いますが、中国語版ウィキ「葉蒨文」によると、今回『山河ノスタルジア』に「珍重」を使ったのも、「彼女の歌は多くに人にとって、ある時代の象徴となっているからだ」とジャ・ジャンクー監督は語っているとか。タオやミアと同様に、「珍重」を聞くとジャ・ジャンクー監督にも昔の感情がよみがえって来るのでしょう。
![]()
(C)Bandai Visual,Bitters End, Office Kitano
『山河ノスタルジア』では、チャオ・タオと共に強い印象を残してくれた俳優が2人います。リャンズー役のリャン・ジンドンと、成長後の息子ダオラー役のドン・ズージェンです。リャン・ジンドンは『プラットホーム』にも出ていたとのことですが、当時は全然気がつきませんでした。本作では、気弱そうに見えて芯の強い炭鉱男を演じていて、ジンシェン役の人気者チャン・イー(『最愛の子』にも出演)よりも光っています。もう一人のドン・ズージェンは、昨年の東京国際映画祭で主演作が2本上映されたように、若手の売れっ子です。東京国際映画祭の作品『少年バビロン』と『少年班』ではあまりいいとは思えなかった彼ですが、本作ではシルヴィア・チャン相手に堂々たる演技を見せてくれて、違った印象を与えてくれました。英語も達者なので、今後は国際派の俳優としても活躍するかも。このように俳優のアンサンブルも素晴らしい『山河ノスタルジア』、冬季に凍ってしまう河など、中国内陸部の目を奪われる景色も見られますので、ぜひ大きなスクリーンでどうぞ。
![]()
(C)Bandai Visual,Bitters End, Office Kitano
なお、本作では、途中で画像のサイズが変わるという、侯孝賢(ホウ・シャオシェン)監督作『黒衣の刺客』のような処理がされている部分があります。その理由は...。ぜひパンフレットを買って、種明かしをお読み下さいね。「そうだったの~」と驚かれること請け合いです。
映画『山河ノスタルジア』予告編
で、ここでちょっと追記を。先日の香港国際映画祭レポートで、『美好合一2016』のことをこちらで取り上げ、オムニバス4作のうちの1作がジャ・ジャンクー監督作品だとお伝えしました。下は、その時の舞台挨拶に登場したジャ・ジャンクー監督とチャオ・タオです。
![]()
ジャ・ジャンクー監督作品「營生(生計を立てる)」は、中年男3人が主人公。演じるのはリャン・ジンドン、『長江哀歌』の韓三明(ハン・サンミン)、そして原文倩(ユン・ウェンチン)という、ジャ・ジャンクー作品お馴染みの3人組。3人は職場は違えども同じ工場で働いていたのですが、警備室にいるのに惰眠をむさぼったり、食堂での仕事がのろかったりしてクビになってしまいます。3人はスマホであれこれ職探しをした結果、「ジャ社長(ジャ・ジャンクー自身が演じています!)が用心棒を募集しているぞ」と求人に応募。でも、年齢制限の24才を超えているし、武術の心得もないし、で3人とも不採用という結果に。結局地元の観光課が募集した、汾陽の歴史を再現するドラマの役者として採用されます。でも、演じている最中に「皇帝はニヤニヤするな」と怒られたジンドンが「皇帝に会ったことあるのかよ」と口答えしたり、サンミンがタバコを吸ったり、「兵士の衣裳は明朝なのに、皇帝の衣裳は清朝だし、変だよ」と文句を言ったりして結局クビに....。
![]()
提供:香港国際映画祭
上は、皇帝役の扮装をしたリャン・ジンドンです。3人とも『山河ノスタルジア』に出ていたので、何となく『山河ノスタルジア』の裏版というニオイもするこの短編映画、「仲良しさんたちが作っている映画」という感じで実にほほえましく、ジャ・ジャンクー作品の好きな人には大いにウケること間違いなし。『山河ノスタルジア』の勢いをかって、ぜひ日本でも『美好合一2016』を公開してほしいですね。