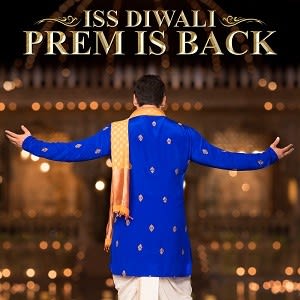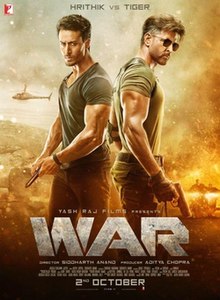『燃えよスーリヤ!!』、いよいよ明日から公開です。ミルクボーイの「コーンフレーク」で笑っている場合ではありません。劇場では美麗&凝りに凝ったパンフレットも皆様をお待ちしています。私も書かせていただいたので早めに頂戴したのですが、画像満載、それもカットアウトが40点近く使ってあり、集中線も多用、怒りマーク、涙マーク等も使い放題という超労作です。編集さん、デザイナーさん、生きてますかぁ~。
![]()
![]()
判型がプレスのA4からB5になったので、裏表紙が「映画秘宝」みたいじゃなくなってしまったのが残念ですが(いや、「映画秘宝」が休刊で無くなってしまうのがもっと残念ですが)、これはインド映画ファンだけでなく、中華系アクション・ファン、ドラゴンファンの方にも必携の1冊です。忘れずにお求め下さいね。
そしてこのブログでは、皆様がご覧になったあと絶対歌いたくなるエンドロールの主題歌「ラッパン・ラッピ・ラップ」の歌詞をアップしておきました。下の特別ミュージックビデオを見ながら、映画を思い出して一緒に歌って下さい。(歌詞が速くて結構難度が高いので、舌をかまないようにご用心)
インド映画『燃えよスーリヤ!!』特別ミュージックビデオ
歌 ♫ Rappan Rapi Rap ♫
ア・ア・イ・イ・ウ・ウ・エ
Aaa..ee..uuu..aee
オ・エ・イ・ア・ホーター・テー
Oo..ae..ee aa hota te
キス・メーン・ティキー・ゴーリー・ティー、ヴェー
Kisme tikhi goli thi, ve
どこに容赦のない銃弾があったんだ
ターキ・ティーキー・ターキー・テー
Taki thiki thaki the..
![]()
©2019 RSVP, a division of Unilazer Ventures Private Limited
ダルター・トー・マィン・シェール・セー・ビー・ナヒーン、レー
Darta to main sher se bhi nahi re
オレは虎だって恐くない
パル・コックローチ・ケー・アーゲー・キャー・カレーン
Par crockroach ke aage kya kare..
だがゴキブリの前じゃどうすりゃいい
トゥー・ミスター・インディア・ナヒーン、ナヒーン
Tu Mr. India nahi nahi..
お前はミスター・インディア*じゃない、ない (*1987年の同名映画の透明人間ヒーロー)
![]()
©2019 RSVP, a division of Unilazer Ventures Private Limited
ウレー・ウレー・チャレー・チャレー
Ude ude chale chale
飛べ飛べ 行け行け
トゥ・ア・ギャラクシー・ファー・ファー・アウェイ
To a glaxy far far away
銀河まで遠く 遠くに
ウレー・ウレー・チャレー・チャレー
Ude ude chale chale
飛べ飛べ 行け行け
アージャー・メーリー・スペース・シップ・メーン・バイト・ジャー・レー
Aaja meri space ship mein baith ja re
来いよ オレの宇宙船に座ってくれ
ウレー・ウレー・チャレー・チャレー
Ude ude chale chale
飛べ飛べ 行け行け
バック・トゥ・ザ・フューチャー、ウ・ア・エ
Back to the future uuu..aaa..aee
バック・トゥ・ザ・フューチャーさ
ウレー・ウレー・チャレー・チャレー
Ude ude chale chale
飛べ飛べ 行け行け
クードーン・スペース・ペー
Kudon space pe..
飛び込もう 宇宙へ
![]()
©2019 RSVP, a division of Unilazer Ventures Private Limited
ラッパン・ラッピ・ラップ
Rappan rapi rap
アンデーローン・ラートーン・メーン・スンサーン・ラーホーン・パル
Andheron raton mein sunsan rahon par
暗い夜に人気のない道で
ラッパン・ラッピ・ラップ
Rappan rapi rap
ユー・ビー・レディー・ウィズ・アーンコーン・カー・レーザー
You be ready with aakhon ka lazor
備えていろ 目のビーム光線を
ラッパン・ラッピ・ラップ
Rappan rapi rap
アプネー・フリーズ・メーン・トゥー・ドラゴンズ・ザマー・カル
Apne freeze mein tu dragons zama kar
自分の冷蔵庫にはドラゴンたちを集めておけ
ラッパン・ラッピ・ラップ
Rappan rapi rap
イェ-・バンダン・トー・ピャール・カー・バンダン・ハィ
Ye bandhan to pyaar ka bandhan hai…
この結び付きは愛の絆だ*(*『カランとアルジュン』(1995)の歌からイタダキのフレーズ)
![]()
©2019 RSVP, a division of Unilazer Ventures Private Limited
パープ・コー・ザ(ジャ)ラー・ザ(ジャ)ラー・ケー・ラーク・カル・ドゥーンガー
Paap ko zala zala ke raakh kar doonga
罪人を燃やして灰にしてやる
ティース・コー・キラー・キラー・ケー・サート・カル・ドゥーンガー
30 ko khila khila ke 60 kar doonga
30をもて遊んで60にしてやる
ティース・カビー・シーダー・サート・ナヒーン・ホーター
30 kabi seedha saath 60 nahi hoota
30はすんなりと60になるもんか
サーティー・フォーティー・フィフティー・シックスティー
30, 40, 50, 60..
![]()
©2019 RSVP, a division of Unilazer Ventures Private Limited
ギブリ・バブリ・ブブリ・バブリ・ビバ・ブブラ
Gibri babri bubri babri biba bubla
ビッグ・トラブル・リトル・チャイン・イン・カラテ・チョップ
Big trouble little chain in karaate chop
大きなトラブルとわずかの平安があるのが空手チョップ
エンター・ザ・ドラゴンズ・フォー・フュー・ドラー・モア
Enter the dragons for few dollar more
『燃えよドラゴン』になるのもはした金のため
メーレー・パース・チュッター・ナヒーン・ナヒーン・ナヒーン
Mere pass chutta nahi..nahi..nahi…
オレの懐には小銭がない、ない、ない
![]()
©2019 RSVP, a division of Unilazer Ventures Private Limited
ウレー・ウレー・チャレー・チャレー
Ude ude chale chale
飛べ飛べ 行け行け
モーグリ・コー・シェール・カーン・セー・バチャーネー
Mogli ko sher khan se bachane
モーグリをシア・カーン*から助けるため (*『ジャングルブック』日本版の名前表記)
ウレー・ウレー・チャレー・チャレー
Ude ude chale chale
飛べ飛べ 行け行け
ドラゴン・ステージ・メーン・ハラー・ケー・ディカー・レー
Dragon stage mein hara ke dikha re
ドラゴンをステージで負かしてみせろ
ウレー・ウレー・チャレー・チャレー
Ude ude chale chale
飛べ飛べ 行け行け
アーエー・バレー・キーレー・バットマン・コー・カーネー
Aaye bade keede batman ko khaane
来たぞ 大きなウジ虫バットマンを喰うために
ウレー・ウレー・チャレー・チャレー
Ude ude chale chale
飛べ飛べ 行け行け
ヘーマー・レーカー・ジャヤー・スシュマー(女性の名前)
Hema Rekha Jaya Sushma…
![]()
©2019 RSVP, a division of Unilazer Ventures Private Limited
ラッパン・ラッピ・ラップ
Rappan rapi rap
アンデーローン・ラートーン・メーン・スンサーン・ラーホーン・パル
Andheron raton mein sunsan rahon par
暗い夜に人気のない道で
ラッパン・ラッピ・ラップ
Rappan rapi rap
ユー・ビー・レディー・ウィズ・アーンコーン・カー・レーザー
You be ready with aakhon ka lazor
備えていろ 目のビーム光線を
ラッパン・ラッピ・ラップ
Rappan rapi rap
アプネー・フリーズ・メーン・トゥー・ドラゴンズ・ザマー・カル
Apne freeze mein tu dragons zama kar
自分の冷蔵庫にはドラゴンたちを集めておけ
ラッパン・ラッピ・ラップ
Rappan rapi rap
イェ-・バンダン・トー・ピャール・カー・バンダン・ハィ
Ye bandhan to pyaar ka bandhan hai…
この結び付きは愛の絆だ
![]()
©2019 RSVP, a division of Unilazer Ventures Private Limited
「劇場でキミを待ってるよっ!」
<追記>
タイミングよく「BANGER!!!」が記事を出して下さいました。ありがとうございます~♥。あと「ガジェット通信」にも、本作に関連して「インド映画インタビュー」記事を載せていただきました。こちらも、ありがとうございました~♥♥。































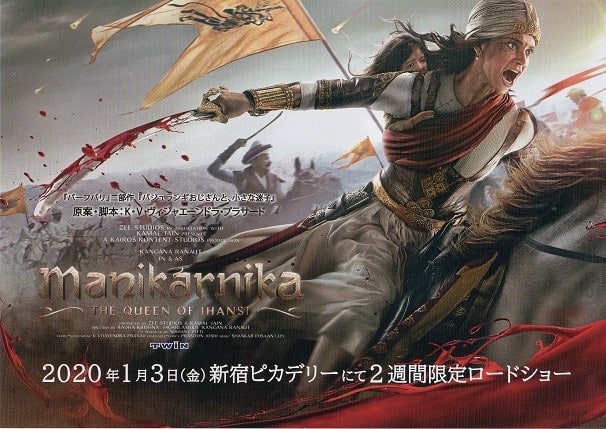



























![あなたの名前を呼べたなら [DVD]](http://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91L-LSfHHyL._AC_UL320_SR226,320_.jpg)
![ラクシュミー 女神転聖 [DVD]](http://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71r%2BtllHFHL._AC_UL320_SR226,320_.jpg)
![ホテル・ムンバイ [DVD]](http://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81fZPMFH4%2BL._AC_UL320_SR226,320_.jpg)
![シークレット・スーパースター [DVD]](http://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71o85m0vg6L._AC_UL320_SR206,320_.jpg)
![ヒンディー・ミディアム [DVD]](http://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71MAWBuiR2L._AC_UL320_SR206,320_.jpg)