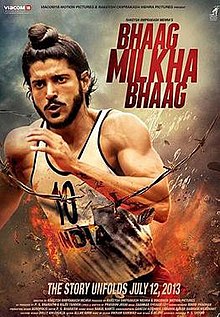昨日、今日と、コンペ作品の西アジア映画を続けて見ました。今年からプレス&IDカード所持者向け試写では、上映後に同じ会場にゲストが登場、笠井アナウンサーが司会してのQ&Aが行われる、というスタイルになり、別会場を設定しての記者会見はなくなりました。便利と言えば便利なのですが、スクリーン前が狭くてゲストにもスタッフにもお気の毒。それと、間近で写真が撮れるいい機会なのに、ストロボがどうも禁止みたいで、私のボロカメラではいろいろやっても満足のいく写真が撮れず、それにもがっくり。今度、仕事料が入ったら軽くて性能のいいカメラを買おうと思います(と、毎年言っている気が...)。
では、2作品の簡単なご紹介とQ&Aのこちらも簡単なレポートを。
『カランダールの雪』
トルコ・ハンガリー/2015年/トルコ語/139分/原題:Kalandar Soğuğu
監督:ムスタファ・カラ
主演:ハイダル・シシマン、ヌライ・イェシルアラズ、ハニファ・カラ
![]()
オープニングタイトルの前に、暗闇が写り、懐中電灯の光の中で岩盤を削っている男の姿が浮かび上がります。この人はどこかに閉じ込められて脱出しようとしているのか、それとも、何か目的があってこの岩盤を削り取ろうとしているのか--下に付けた予告編(?)の冒頭にも出てくる緊張をはらむこのシーンで、観客はぐっと映画の中に引き込まれます。
それが主人公のメフメット(ハイダル・シシマン)で、鉱石を捜して険しい山に登り、鉱脈がありそうな所のサンプルを取っては、麓の精錬工場に売り込むという作業が続きます。貧しい彼の家には、年老いた母親と妻、ミドルティーンの長男と、障がいを持つ幼い次男がいます。山中の一軒家であるこの家は、家畜を飼い、わずかな畑を作り、時にはカタツムリを獲って売るなどして、かつかつの生活をしています。メフメットはうまくいかない鉱脈捜しを一時やめて、祭りの時に開かれる闘牛で勝って現金を手に入れようと、雄牛ポイラズの訓練を重ねるのですが....。
ラストは寓意に満ちたハッピーエンドとも言える終わり方なのですが、そこに到るメフメット一家の苦闘を、映画は1年にわたって描いていきます。トルコの黒海に近い地域、とのことですが、冬山に轟く雷鳴や、小屋と言ってもいいような家を押しつぶさんばかりの雪、山中であっという間に周囲を包む霧など、四季折々の自然も苛酷で、見ていてだんだん肩が重くなってくる感じがします。とはいえ、最後まで緊張感を保って見ていられるのは、その自然の中での人間の営みがきっちりと描かれているから。子役の二人や祖母も存在感に溢れ、特にダウン症の男の子が演じている次男は、時折ハッとするような表情を見せてくれます。監督の演出の底力を感じさせてくれる作品でした。
COLD OF KALANDAR
<ゲスト>
監督:ムスタファ・カラ
プロデューサー:ネルミン・アイテキン
脚本:ビラル・セルト
主演:ハイダル・シシマン
![]()
右から上の通りの皆さんですが、プロデュ-サーが若い女性でちょっとびっくり。あれだけの大作を作るのは大変だったでしょうに。時間的にも2時間半近い作品なのですが、それと共に撮影期間も長期にわたっているはずで、統括は相当の力技を必要としたのでは、と思います。
監督:本作では、以前私が知っていた人のキャラクターを再現してみました。主人公をこれほどの情熱に駆り立てるものは何か、彼の関心はどこにあるのか、家族との葛藤はどうなのか、どんな形で自己証明をしているのか、といった、次々に出てくる疑問に答を出していたら、ストーリーが出来上がりました。
![]()
Q:主演のハイダル・シシマンさんにうかがいたいのですが、厳しい自然の中、いいことは最後まで起きない、という状況の中で、主人公を演じてみてどうでしたか。
ハイダル・シシマン:メフメットの自然との闘いは、勝つか負けるかのどちらかです。その中で彼の情熱を表さなければいけないと思いました。自然と希望とが衝突し、最後には希望が勝つ。メフメットが持っている希望が、私自身にも大きな影響を与えてくれました。撮影現場ではメフメットになり切っていたので、撮影が終わってもしばらくはメフメットから離れられませんでした。
![]()
Q:題名にもなっている「カランダール」ですが、これは祭りの名前とかで、その時に闘牛がある、ということですか?
脚本:カランダールはある季節の名称です。とても寒い夜の名前で、この地域に住む人々にとっては、ある慣習を表す言葉にもなっています。
![]()
Q:撮影が大変だったと思いますが、エンドロールにヌリ・ビルゲ・ジェイラン監督らの名前が出ていたのは、何か協力があったということでしょうか?
監督:あそこに名前を挙げた監督たちは、トルコ国内のみならず、世界的にも知られている重要な監督たちです。物語の構想段階から始まって、撮影が終わったあとに到るまで、彼らは様々な面でサポートしてくれました。撮影の困難さについては、それを話すだけで一つの物語ができてしまうぐらい、たくさんありました。ご覧になったように、映画には4つの季節が描かれています。そこにある人々の生活、小さな生き物たちの営み、といった細部に到るまで、撮影のたびに同じものを作らないといけなかったのです。でも、映画の中の現実性を観客にキャッチしてもらうには、自然のルールの中に我々自身が入っていき、一体となって映画に描かれる必要がある。こういったことから、物質的にも経済的にもすごく大変な作品となりました。
![]()
『ガールズ・ハウス』
イラン/2015年/ペルシャ語/80分/原題:Khane-ye Dokhtar(?)/Khane Dokhtar(?)
監督:シャーラム・シャー・ホセイニ
主演:ハメッド・ベーダッド、ラーナ・アザディワル、ババック・キャリミ
![]()
こちらの作品は、友人サミラの結婚式を明日に控え、二人の若い女性、バハールとパリサがその支度のためにショッピングをするシーンから始まります。二人は大学生で、「学生さんなら負けておいてあげるよ」という店主とやり取りしながら、楽しそうにおしゃれな靴を選んでいきます。途中で花嫁サミラに電話したり、彼女の妹セターレとバッタリ会ったりして、遅くなって学生寮に戻ってきたところに電話が入ります。それは、サミラの突然の死を知らせる電話で、明日の結婚式は中止になった、という連絡でした。二人はサミラの突然の死に納得できず、彼女の家を訪ねたり、墓地へ行ってみたり、そこで出会った花婿マンスールと話して、死の真相を探ろうとするのですが....。
前半は、サミラの死に関するサスペンスが追求されていき、後半で時間が巻き戻されて、彼女の死(実は自殺)に到った経緯が解き明かされていきます。幸不幸の入り交じり方がちょっとあざとい感じもしますが、上の写真が象徴するサミラが受けたショックが最後には明らかになり、ある意味すっきりした終わり方となります。そんなショックなことをなぜ結婚式の前日に? という疑問も残るものの、まだまだ保守性の残る現代イランの側面を伝える作品、とも言えそうです。
![]()
<ゲスト>
監督:シャーラム・シャー・ホセイニ
主演:ハメッド・ベーダッド
おしゃれなホセイニ監督(右)と、マンスール役を演じた俳優ハメッド・ベーダッドです。ハメッド・ベーダッドはイランでは人気のある俳優なのだとか。IMDbを見てみると、29本の出演作がクレジットされています。1973年マシュハドの生まれ、とありますから、もう40才を過ぎているんですね。通訳は、皆様お馴染み、ショーレ・ゴルパリアンさんです。
![]()
Q:この映画では、古い因習に対する抗議が見て取れますが。
監督:本作はそういう因習を批判する映画でもありますが、疑問を呈する形で、答を出していない映画とも言えます。映画を見る人それぞれに、判断を任せているのです。
![]()
Q:マンスールは高卒、かたやサミラは大学生。またサミラは「自由に生きる」という詩が好きだったりしますが、一方で式場を男女別に分けることにしたりと、保守的な面もあります。また、サミラの妹は出かけた時にボーイフレンドとデートしたりもする。そんなサミラは、マンスールの母に強制されたことがショックだったのでしょうか? タイトルの「ガールズ・ハウス(原題:ハーネ・イェ・ドフタル=娘の部屋)」の意味するところは?
監督:多分、長い時間をかけて説明しないとわかってもらえないかと思います。ただ、イランは社会的にレベルが違う人でも結婚できる、という点は誇っていいと思いますよ。日本では嫁姑関係が厳しい、というのを、私は日本の映画から学びました。本作でも、花嫁に対する婚家の姑の厳しい目、というのが問題の一つになっています。
主演俳優:確かに、本作では女性が大学卒で男性が高卒ですが、男性の場合は家族を養うことを学歴よりも優先させる場合があります。長男は高校を終えたら働いて、家族の女性に学ぶ機会を与える、ということもあるんです。
監督:タイトルが意味するものですが、映画の中では観客に「ガールズ・ハウスとは何か」という説明はしていません。これは、彼女自身の内面にあるテリトリー、スペースといった意味合いがあります。自分の中にある「ガールズ・ハウス」に入る時は、ノックして入ってきてほしい、そいう意味のあるタイトルなんです。
![]()
Q:自殺がどう描かれるのかは、国によって違うと思います。今回の作品では、サミラが自殺したことにより父は家を売ろうとする、というのが出てきますが、それは自殺がまずいから、ということですか?
監督:イランでは、家族、宗教、人間関係、そして思いやりがとても大切です。自殺はもちろん宗教上でも罪となりますが、人間関係から見ても非常に罪深いことになってしまいます。だから、サミラの家族はそれを隠そうとするのです。しかしながら、自殺したことを隠し、葬式もせずに逃げるように去って行く、というのはもっと悪いと思いますね。
![]()
Q:ハメッド・ベーダッドさんにうかがいたいのですが、マンスールを演じながら、個人的にはこの映画についてどのように思っていましたか?
主演俳優:ある役を演じる時は、その中に自分を入れ込んで演じています。物語が持つメッセージを、演技の中に入れて演じるように心がけているのです。自殺はイスラーム教では悪いことと考えられていますが、これは人間にとって死はいつか訪れるものなので、こちらから死ぬのは間違い、ということからです。本作では、サミラの死に対して、父親が冷たすぎる気がします。死んですぐ、家を売りたいと言ったりしますが、本当のお父さんなのか疑りたいぐらいです。母親が再婚した相手とかではないか、と思ったりしました。
監督:いや、本当の父親だよ。
ショーレ・ゴルパリアン:では、その論争はまた外で、ということで(笑)。
![]()
YouTubeに予告編が挙がっていましたので、付けておきます。
- ????? ???? ???? ????
最終日、31日(土)の受賞結果に注目しましょう!