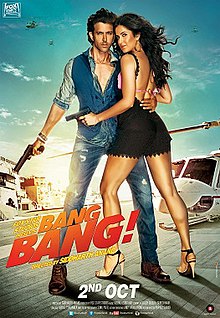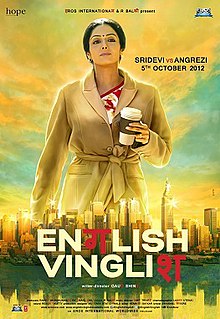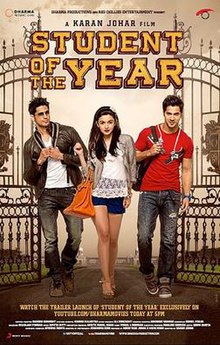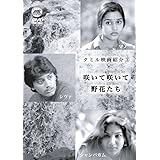フィルメックスも11月28日に受賞結果が発表されたのですが、まだ「特集上映 ツァイ・ミンリャン」が継続中なので、報告の続きを書いてしまいます。なお、有楽町スバル座で上映中の「特集上映 ツァイ・ミンリャン」に関しては、フィルメックスのサイトをご覧下さい。12月4日(金)まで上映があります。
さて、残る報告は11月26日(木)と27日(金)に関してなのですが、どちらにも張艾嘉(シルヴィア・チャン)関連の作品があったので、まずその2本をご紹介しましょう。
『華麗上班族』
中国、香港/2015年/118分/原題:華麗上班族/英語題名:Office
![Office 2015 poster.jpg]()
![]()
監督:ジョニー・トー(Johnnie TO)
主演:周潤發(チョウ・ユンファ)、陳奕迅(イーソン・チャン)、張艾嘉(シルヴィア・チャン)、湯唯(タン・ウェイ)、王紫逸、郎月婷、車婉婉(ステファニー・チェ)、張兆暉(エディー・チョン)、洪天明(ティミー・ハン)
元々はシルヴィア・チャンの原案・出演による舞台劇だったそうで、それをジョニー・トー監督が映画化したものです。そのあたりの経緯については、上映後のQ&Aでシルヴィアが語ってくれました。出演者たちもほぼ全員が自分で歌っているのですが、チョウ・ユンファの歌うシーンがない理由はQ&Aでシルヴィアがいきさつを暴露してくれていますので、そちらをどうぞ。
全体としては、舞台劇ミュージカルのためストーリーに深みはないものの、現在の中国、あるいは香港のオフィスにおける人間模様をよく捉えていて楽しめます。何よりも張叔平(ウィリアム・チャン)のセットが斬新で、それが目に楽しいのです。一番素敵だったのは、スケルトンの地下鉄車両。うまくボディを切り抜いてあって、出てくるたびに目が引きつけられました。さらに、斬新なセット空間を生かす撮影や、場面転換のうまさなども、やはりジョニー・トー監督ならではと言えます。多分、撮っていたトー監督自身が一番楽しんでいたのでは、と思える作品でした。
![]()
出演者もハマリ役と思える人が多く、イーソン・チャンはイヤミな副社長で、シルヴィア・チャン扮する社長と肉体関係もある役を大熱演。破滅に向かう時に、車を運転しながら歌うナンバーは印象に残りました。シルヴィアの役は、会長のチョウ・ユンファの愛人としてのしあがってきた女性社長なんですが、年下のイーソンも手玉に取っている凄腕女性。こんないわば悪女役を演じさせても、実にうまいですね。タン・ウェイ始め、脇を固めるトー監督組のステファニー・チェ(もともと歌手ですもんね)やエディー・チョンも達者に歌っていました。
ただ、私的に不満だったのは、主人公とも言える新入男性社員李想役の王紫逸がいまひとつのご面相だったこと。「残念なカン・ドンウォン」(笑)というか、東MAXというか....。女性新入社員役の郎月婷の方は、清楚系の美女でよかったんですけれど。それで、彼が出てくると気分が盛下がってしまい、ちょい残念でした。
というわけで、シルヴィア・チャンのQ&Aをどうぞ。通訳はいつもお馴染み、でもフィルメックスでは初登場のサミュエル周先生です。
![]()
Q:(まず、司会のフィルメックス・プログラム・ディレクター市山尚三さんから)この作品は、どういう経緯で映画になったのですか?
シルヴィア・チャン(以下”A”):2008年に、台湾の監督林奕華さんが、舞台劇をやりたい、と私にアプローチしてきたのです。何を描こうかと考えて、サラリーマンを主人公にすることにしました。(調べてみると、舞台劇のタイトルは「華麗上班族之生活與生存」)それで、2008年に上海で上演した時にジョニー・トー監督が見に来て、「これ、僕が監督して映画にしたい」と言い出したんです。その時は、「冗談でしょ」と思いました(笑)。映画にするなら私自身が監督したいと思っていたのですが、なぜかトー監督がメガホンを取ることになってしまいまして。
![]()
Q:セリフは普通話(標準中国語)と広東語が混じっていますが、どう使い分けられているのですか? 中国で上映の時もこのままの言語で?
A:トー監督とも話し合ったのですが、舞台はどこか大都会、ということで、香港でも上海でも北京でもあてはまる場所です。だから、出演者たちがぞれぞれ自分の言葉をしゃべればいい、ということになりました。セット撮影ですが、音声をそのまま取ることができない場合もあったので、一部はアフレコです。中国での公開時は、中国側の希望により全部北京語(=普通話)のヴァージョンで上映しましたが、それ以外の所での上映はこのヴァージョンです。
![]()
Q:昔の作品『過ぎゆく時の中で』(1989)以来の、ジョニー・トー監督作品でのチョウ・ユンファとの共演ですね。久しぶりに共演なさってどうでした?
A:2人とも変わりましたからね。もちろん年を取りましたし、ユンファはさらにインターナショナルな俳優になっていますし。でも、映画が大好きというのは2人とも全然変わっていません。10日ほどの撮影のうち、ユンファの撮影の時は、時間がオーバーするとギャラをよけいに払わないといけない(笑)からというので、出番が終わったら「どうぞどうぞ、お帰り下さい」と彼は言われていたんですが、でもよく現場に残って見ていました。残念だったのは、私と彼との共演場面が少なかったことで、次にはもっと長く共演できる作品をやってみたいです。
![]()
Q:キャスティングはどのようになされたのでしょうか?
A:トー監督からは、「歌は歌ってもらうけど、ダンスは要らない。中国人はダンスが下手だから」と言われました。ダンスをするシーンがあったとすると、すごく練習をしないといけなかったでしょう。歌に関してユンファは、「絶対歌いたくない。殺されても歌いたくない」(笑)と言ってました。
というわけで、会長が歌わないわけですから、副社長のキャスティングが重要になってきます。そう考えると、イーソン・チャンしかいない、ということで彼になりました。タン・ウェイも最初歌うのを心配していて、できるかしらと言っていたのですが、いざ歌ってみると楽しくなったようで、自分でやり遂げました。
![]()
Q:スケルトン・セットのアイディアはどなたが?
A:トー監督のアイディアです。最初舞台をどこにするかという話し合いをした時、場所は大都会のオフィスで、何でも見えてしまうというセットにしよう、というアイディアが提示されました。心の中にしか秘密がない、というのを表すために、全部スケスケのセットになったのです。もう一つ大事だったのは階段で、2008年の舞台劇の時もしつらえられていたのですが、登場人物の上昇志向を象徴するものです。それをウィリアム・チャンがうまく取り込んでくれました。全体として、鉄の網目の中にいる人間、動物のように檻の中にいる人間に見えるように、ああいうセットになったのです。
![]()
Q:トー監督は昔、『シェルブールの雨傘』が好きだ、と言っていらしたと思うのですが、映画もミュージカルにしたのはトー監督の判断ですか?
A:ミュージカルに、というのは私のアイディアです。私はミュージカルがとても好きなんです。中国人はいつも話し方が曖昧ですが、歌にするとハッキリ言わざるを得なくなる。舞台は3時間30分のものだったのですが、映画は2時間に縮めたので、撮る時はまるでアクション映画を撮っているみたいでした。
『華麗上班族』の予告編はこちらです。
[電影預告]《華麗上班族》(OFFICE),9月24日,華麗獻映
『念念』
台湾、香港/2015年/119分/原題:念念/英語題名:Murmur of the Hearts
![Murmur of the Hearts film poster.jpg]()
監督:張艾嘉/シルヴィア・チャン(Sylvia CHANG)
主演:梁洛施(イザベラ・リョン)、張孝全(ジョセフ・チャン)、柯宇倫(クー・ユールン)
![]()
こちらの作品の感想は、以前香港国際映画祭で見た時にアップした記事をどうぞ。この日Q&Aに登場したシルヴィア・チャンは、前日とは変わって鮮やかなブルーのお洋服。この日の通訳は渋谷裕子さんです。
![]()
Q:(口切りの質問は、司会のフィルメックス・ディレクター林加奈子さんから)脚本のクレジットがシルヴィア・チャンさんんと蔭山征彦さんというお名前になっていますが、日本人の方ですか?
A:この映画を撮るのは、運命だったと思っています。なぜかこの脚本が私の机の上に乗っていたんですよね。それを読んだ時、心が痛くなりました。若い男性の家族への思い、そしてわだかまりというものが幻想的に表現されていて、私も1人の母親としてとても惹きつけられました。(蔭山征彦さんは台湾で俳優として活躍している人で、元々は彼が書き上げた脚本だったのだとか)
![]()
Q:女優さんのキャスティング、特に主役のイザベル・リョンさんのキャスティングについてうかがいたいです。また、母親役のアンジェリカ・リーさんが「絵画」のところにもクレジットされていますが、これは?
A:まず2つ目の質問にお答えすると、映画に登場する油絵はすべて、アンジェリカ・リーが描いたものです。最初は地元の画家にお願いしようと思ったのですが、男性画家なので女性の心をうまく表現できず、ダメでした。続いて女性画家に依頼したものの、今度は母性が出ていなくて不満に思いました。それでアンジェリカに頼んだら、さすが画家だけあってピッタリの絵を描いてくれました。
1つ目の質問ですが、ヒロインを誰にするかで、ずっと悩んでいたんです。ちょうどその頃イザベラ・リョンがカナダから帰ってきて、話をしてみたところ、「長い間脚本も読んでないし、映画にも出ていない」という心情をひしひしと感じました。そして、「ここに私のヒロインがいる!」と思ったわけです。心の芯の強さを感じさせてくれる、理想的なヒロインでした。
![]()
Q:膨大な物語があって、いっぱい撮ってから編集して切ったような感じを受けました。元の脚本とはどのくらい違っているのでしょう?
A:内面というか、感情を描いた作品なので、ストーリーテリングは念頭に置いていません。ですので撮影の時は脚本の存在を忘れて、役者が醸し出す雰囲気に従って撮っていこうと思いました。今回の映画製作では、これまでになかったようなことが不思議といろいろ起きました。いつもは二度撮りなんてしたことないのに、舞台となった緑島に情景だけ再び撮りに行くことになったり、日本人の経営するバーのシーンも、4回も撮り直しに行ったり。撮り終えてから9ヶ月間を編集に費やしたのですが、日本人のバーでは何度も撮り直しをお願いしたせいで、「また来たのか」と嫌がられました(笑)。
![]()
Q:緑島は「緑島小夜曲」でも知られていますし、あと「火焼島」としても知られていますが、あそこを舞台にしたのはなぜですか?
A:「緑島小夜曲」の「緑島」は台湾全体のことを指しています。必ずしもあの緑島ではないので、本作の中ではあの曲を使用しませんでした。映画の中で使った曲は、「台北の空」という1980年代初めの曲です。これは、主人公たちの母親の夢と希望、緑島から出て大都会=台北に行きたい、という気持ちを托す歌として使いました。
緑島という設定は元々の脚本には書かれていなくて、当初の舞台は台湾と北海道でした。でも、実際に撮影するには離れすぎていて難しい、ということで、台湾島の東側にある離島の緑島にしました。緑島は以前は刑務所がいくつもあり、「火焼島」とも呼ばれましたが、今は刑務所も1つだけになっています。観光化が進んで、ダイビングの名所ともなっている所です。
![]()
(「台北の空(台北的天空)」(1984)はこちらで聞けます)
王芷蕾 - 台北的天空 / Taipei's Sky (by Jeanette Wang)
Q:イザベラ・リョンが演じるユーメイの衣裳が気に入りました。何かこだわりとかあったのでしょうか。また、日本人経営のバーの名前が「藤」でしたが、それにも何か意味が?
A:出演者1人1人のキャラクターを決めるデザインには凝りましたが、イザベラは何を着ても似合う人でした。でも私が一番好きな衣裳は、ジョセフ・チャンが着ていた何の変哲もない、うすいピンク色のTシャツです(笑)。
「藤」は台湾で30年以上にわたって、日本人が経営している会員制のバーです。私はそれまで連れて行ってもらったことがなかったんですが、30年前の内装を変えずにそのまま使っているので、昔の姿を残しているお店です。最近はさすがに客が減ってきていたようでしたが、この映画に登場したので、また客が増えたそうです(笑)。
![]()
時にユーモアも交えて、はきはきとかつ気さくに答えてくれるシルヴィア・チャン監督。とってもチャーミングな人でした。『念念』の予告編はこちらです。
念念 Murmur of the Hearts (2015) Official Hong Kong Trailer HD 1080 Isabella Joseph Chang HK Neo