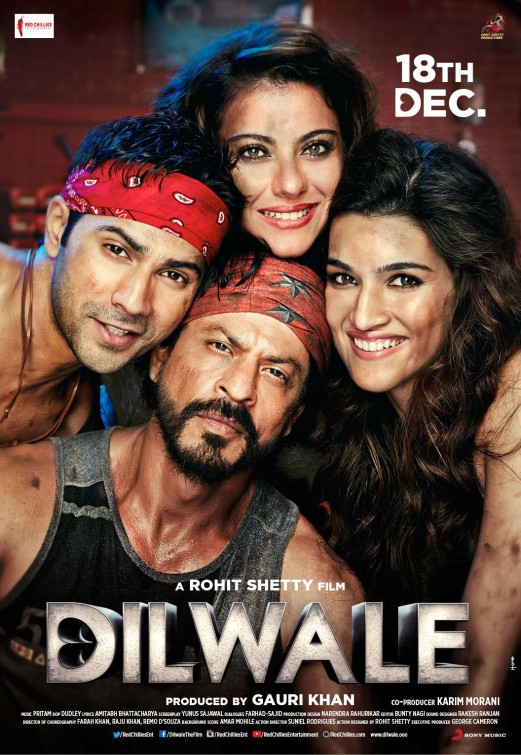さてさて、インドに来ていても、気になるのは日本の情勢。といっても「もり・かけ」問題の情勢ではなく、『ダンガル きっと、つよくなる』をめぐるあれこれです。4月6日(金)の公開まで1ヶ月を切ってしまい、宣伝もいよいよ佳境に入っている時ですね。こちらでもcocoのツイッターをよくチェックしているのですが、宣伝にツッコミどころが多くて、それを読むたびに少しだけ関係者の私も背中に冷や汗が流れます。たとえば、「副題:きっと、つよくなる」→テークダウンで2点失う、「純朴なチラシ」→コレクトホールドで1点失う、「川崎のぼる先生のすばらしいイラスト」アップロード@公式サイト失敗(今はちゃんと見られます)→場外でマイナス1点か、と思われましたが、からくも逃げてノーカウント、という感じでしょうか。ギャガさんと共に宣伝を分担しているアニープラネットさんとスキップさん、がんばって下さい!
さて、日本を出る前に画像もたくさんいただいたので、ちょっと登場人物と俳優の紹介をしておきたいと思います。その前に、いつもの基本データをどうぞ。それにしても、川崎のぼる先生のイラストとコメント、すばらしいですね。まだ見ていない方は、下のアドレスから公式サイトに飛んで下さい。

(c)Aamir Khan Productions Private Limited and UTV Software Communications Limited 2016
『ダンガル きっと、強くなる』 公式サイト
2016年/インド/ヒンディー語/140分/原題:Dangal
監督:ニテーシュ・ティワーリー
主演:アーミル・カーン、サークシー・タンワル、ファーティマー・サナー・シャイク、ザイラー・ワシーム、サニャー・マルホートラー、スハーニー・バトナーガル、アパルシャクティ・クラーナー、リトウィク・サホーレー
配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン/ギャガ
※4月6日(金)よりTOHOシネマズシャンテほか全国公開
では、本作で見事な戦いっぷりを見せる登場人物たちをご紹介していきましょう。

(c)Aamir Khan Productions Private Limited and UTV Software Communications Limited 2016
マハヴィル:アーミル・カーン
フルネームではマハヴィル・シン・フォガト(正確に音引きを付けた書き方をするとマハーヴィール・シン・フォーガート。以下、かっこ内は同様)。レスリングでインドのナショナル・チャンピオンとなりますが、家庭の事情からレスリングに生きることはあきらめ、普通の勤め人となります。その後の展開は、いろいろと脚色はあれどほぼ映画に描かれた通り。今では、「フォガト・シスターズ」と呼ばれる女子レスリング選手グループの生みの親&育ての親として名を知られる人です。「フォガト・シスターズ」は実の娘であるギータ(ギータ-)、バビータ(バビータ-)、リトゥ、サンギーターに加え、姪のプリヤンカーとヴィネーシュの6人を指して言います。この姪の2人が、劇中ではオムカルという甥に転化されているようです。

(c)Aamir Khan Productions Private Limited and UTV Software Communications Limited 2016
アーミル・カーンは1965年3月14日生まれなので、明日で53歳。今日の新聞に、「明日は誕生日だけど、今撮っている『Thugs of Hindostan(インドのトゥグたち)』の最後の撮影がジョードプルであるので、ワーキング・バースデーになるんだよ」とコメントが出ていました。
アーミルは父もプロデュ-サー兼監督だったのですが、伯父が有名なプロデユーサー、監督として1960・70年代にヒット作を連発していたため、伯父の作品で子役としてデビューします。大人の役者として認識されたのが、ケータン・メーヘター監督の『Holi(ホーリー祭)』(1985)で、この時は大学寮に住む学生の1人という役柄でしたが、続く従兄マンスール・カーン監督作『Qayamat Se Qayamat Tak(破滅から破滅まで)』(1988)で大ブレイク、ジュヒー・チャーウラー相手に演じた「ロミオとジュリエット」ストーリーは、純愛映画ブームを巻き起こすきっかけとなったのでした。
以後、トップスターとして順調にキャリアを重ね、『Dil(心)』(1990)、『Rangeela(ギンギラ)』(1995)、『Raja Hindustani(インドのラージャー)』(1996)等々、数え切れないヒット作に出演します。その間にもアート系の作品、ディーパー・メーヘター監督の『Earth(大地)』(1998)などに出演して演技力を磨き、2001年、2つの作品で新境地を開きます。1つは日本でも上映されてソフト化されているアーシュトーシュ・ゴーワーリーカル監督の『ラガーン』、もう1つはファルハーン・アクタル監督の『Dil Chahta Hai(心が望んでる)』です。後者は自然体の演技や撮り方で、いわば「21世紀のボリウッド映画」をスタートさせた作品といえ、これを期にアーミルは作品を厳選し、ほぼ年1本の主演作を完璧に撮りあげる「Mr. Perfect」となります。
その後のヒット作は、『きっと、うまくいく』(2009)、『チェイス!』(2013)、『PK』(2014)と日本でも公開されていますが、その他の作品では、『ミルカ』のラーケーシュ・オームプラカーシュ・メーヘラー監督作『Rang De Basanti(愛国の色に染めろ)』(2006)や、『スタンリーのお弁当箱』のアモール・グプテー監督との共同監督にも挑戦した『Tare Zameen Par(地上の星たち)』(2007)などがあります。この『Tare Zameen Par』は中国で大人気となったため、その後アーミルの作品は中国の人々にとって大好きな作品となり、今回の中国での『ダンガル きっと、つよくなる』の大ヒットにもつながりました。
現在撮影中の 『Thugs of Hindostan(インドのトゥグたち)』は、『チェイス!』のヴィジャイ・クリシュナ・アーチャーリヤ監督作品で、共演はアミターブ・バッチャン、カトリーナ・カイフ、そして『ダンガル』のギータ役で一躍有名になった、ファーティマー・サナー・シャイクらです。「トゥグ」は反逆者、強盗・殺人集団としても知られた人々で、どんな映画になるのかまだ情報が流れてきませんが、アーミルが出演を承諾した映画だけに、単なる犯罪映画ではないものと期待できます。
なお『ダンガル』では、若い時にナショナル・チャンピオンになった姿から、年を取るに従って太っていくアーミルが見られますが、下に付けたメイキング映像によると、「それでは、若い時を最初に撮って、だんだんと体重を増やしていってもらいましょうか」と監督が提案したところ、「いや、反対にしてほしい。今からだんだん太るから、その最後にダイエットして若い時を撮って下さい。そうすれば、すぐに元の生活に戻れるから」と言ったようです。メイキング映像では、アーミルがいかにすごい意思の人かが見られます。ぜひ、日本版ソフトに収録してもらいたいですね。
Fat To Fit | Aamir Khan Body Transformation | Dangal | In Cinemas Dec 23, 2016
アーミルだけでも長くなってしまったので、あとは延長戦ということでまた次回に<つづく>。