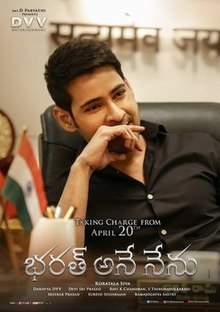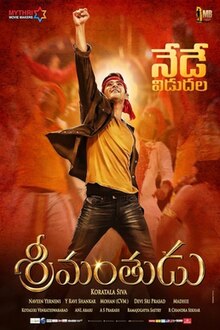さて、舞台挨拶を終えたS.S.ラージャマウリ監督とショーブ・ヤーララガッダ・プロデューサーは控え室へと引き上げてきます。新宿ピカデリーには、ちょっと狭いけどきれいな控え室が複数あって、すぐそばにはトイレも備え付けられているなど、ゲストにとってはありがたい設計になっています。私は今回、配給会社のツインさん、宣伝を担当している祭屋さん、そして宣伝隊長の江戸木純さんにご無理をお願いして、どうしても聞きたいいくつかの質問を監督にさせていただくために、控え室にお邪魔したのでした。休憩時間に申し訳ない、と思いつつうかがったら、監督はオフィシャル写真撮影の真っ最中。場所が狭かったのでオフィシャルのカメラマンが苦労して撮影していたのですが、『バーフバリ 王の凱旋』のポスターと一緒に撮ろうとすると、どうしても天井光がポスターに反射してうまくいきません。すると、困っているカメラマンに監督が、「私がこうやってポスターを傾けてるから」と、天井光を遮断できるようにポスターパネルを少し前倒しにして下さいました。さすが、レフ板を使い慣れている監督、と感心しつつ、気さくな方だなあ、とますます尊敬の念が強くなりました。以下はそんな監督にうかがった、直撃「『バーフバリ』の隅をつつく」インタビューです。オフィシャルの舞台挨拶写真と、『バーフバリ 王の凱旋』のスチールと共にどうぞ。
![]()
©TWIN
Q:監督は小さい頃、神話のマンガ本をよく読んでいた、とうかがいましたが、それは「Amar Chitra Katha(アマル・チットラ・カター/不滅の絵物語↓)」シリーズですか?
![]()
監督:そうです。
Q:読んだ本で、題名を憶えていらっしゃるものがありますか?
監督:私は全冊、出版された物は残らず読んでいます。クリシュナの物語、ラーマの物語などなど、全部読んだんです。合計で400冊ぐらいになるでしょうか。
Q:ええっ、400冊も! すごいですね!
監督:そう、400冊ぜ~んぶ読んだんです。今でも全冊、家に揃ってますよ。
Q:お父様(V.ヴィジャエーンドラ・プラサード)が買って、お与えになったんですか?
監督:父が図書館に連れて行ってくれたんです。子供時代は小さな町に住んでいたのですが、そこに地域の図書館があって、「アマル・チットラ・カター」が全冊揃っていました。そこで読み始めて、大きくなってから自分で買えるようになると、全冊買いそろえました。
(ここで、監督は新宿ピカデリーにプレゼントするポスターにサイン。2枚ありましたので、そのうち皆さんのお目にとまることがあるでしょう)
Q:最近のインドではグラフィック・ノベル(劇画調のコミック本)が流行ってますが、『バーフバリ』をお作りになる時に参照なさったものとかがありますか? 例えば衣装なんかで。
監督:いや、ないですね。むしろ、衣装は「アマル・チットラ・カター」を参考にしました。あの本にはどんな衣装でも載っているので、いろいろ参考にさせてもらいました。グラフィック・ノベルは最近になって少しずつ増えてきてはいますが、画調が西洋っぽいものがほとんどです。だから、あまり参考にはなりませんでした。
![]()
©ARKA MEDIAWORKS PROPERTY, ALL RIGHTS RESERVED.
Q:『バーフバリ 伝説誕生』には、「マハーバーラタ」とシヴァ神の影響が見て取れます。そして『~王の凱旋』では、「ラーマーヤナ」とヴィシュヌ神の影響が出てきていますね。クンタラ国がヴィシュヌ信仰の国として描かれていますが、これは最初からそのような設定になっていたのでしょうか?
監督:マヒシュマティ王国を最初にデザインした時は、非常に厳しい、厳格な政治が行われている軍事国家、というイメージで始めました。そういう国が信仰する神としては、シヴァ神だろうと思ったのです。だから、シヴァ神の姿がいろいろ出てきたわけですね。次にクンタラ国のデザインを考えた時は、そこにはハッピーな人たちが住んでいる、とイメージしました。平和を愛する人々がいる国なので、神様はクリシュナ神がぴったりだと思ったのです。それで、どの部分もそういうイメージで作り上げました。
Q:なるほど。実は日本の観客には、クマラ・ヴァルマのキャラがすごく人気があるんですよ。
監督:アッハッハ。
![]()
©ARKA MEDIAWORKS PROPERTY, ALL RIGHTS RESERVED.
Q:彼は腕っ節は弱いのですが、心やさしくて、面白いですよね。
監督:それも「マハーバーラタ」が下敷きになっています。
(注:調べてみると、「マハーバーラタ」の最後の戦争時に、パーンダヴァの5王子側について殺されることになる王が「クマーラ」という名前のようです)
Q:『~伝説誕生』が完成した時点では、『~王の凱旋』はどのくらい完成していたのですか?
監督:30%ぐらいですね。3割ぐらいが撮影済みでした。
Q:それで、『~伝説誕生』のラストにいくつかのシーンを使われたわけですね。『~伝説誕生』では、実にユニークな部族「カーラケーヤ」が出てきますが、その言語がクリック音の入るもので、あれも独特です。あの部族のアイディアは、一体どこから得られたのですか?
監督:カーラケーヤはですね...(と少し考えて)、バーフバリとバラーラデーヴァはものすごーく強いでしょう? この2人が誰かと戦うとすると、その相手は外見からして、もっと強そうでないといけないわけです。それで私は、衣装デザインを担当した妻(ラマー・ラージャマウリ)に、怪物的な外見のものをデザインしてみてくれ、と頼んだんです。バーフバリとバラーラデーヴァよりももっと強そうな存在を頼む、と言ってね。それで彼女がカーラケーヤをデザインして、ああいう格好にしました。カーラケーヤ族はこんな存在ですから、彼らがテルグ語やタミル語をしゃべるのは全然そぐわない。そう思って私は、タミル語のセリフ作家であるカールキに、彼らの言葉を作り出してくれ、と依頼しました。で、彼が作り出してくれたのがあの言語だった、というわけです。
![]()
©ARKA MEDIAWORKS PROPERTY, ALL RIGHTS RESERVED.
Q:キャラとして強烈で素晴らしいですね。それから、さっきの舞台挨拶でインターナショナル版のお話が出ましたが、このヴァージョンの編集は監督ご自身でおやりになったのですか?
監督:そうです。もちろん編集担当者がいて、技術的には彼(コーターギリ・ヴェンカテーシュワラ・ラーオ)がやったわけですが、指示はすべて私が出しました。
Q:えーっと、『~伝説誕生』のインターナショナル版では、エンドロールの途中から音楽がなくなって、無音になっちゃったんですが...。
監督:え? あ、ああ~(と笑い出す)。
Q:『~王の凱旋』のインターナショナル版は、エンドロールがすっごく短かったですし、見てる私たちは戸惑っちゃいました。
監督:(笑いながら)オーケー、オーケー。今度は<完全版>が公開されるから、ね。
![]()
©ARKA MEDIAWORKS PROPERTY, ALL RIGHTS RESERVED.
Q:監督はどの作品でもインターナショナル版をお作りになるんですか?
監督:いやいや、『バーフバリ』が初めてですよ。『マッキー』も、言語によって編集を少し変えましたけどね。
Q:『マッキー』の配給会社の人が、ヒンディー語版はコメディシーンが切ってあって、少し短くなっているから買った、と言っていました。
監督:そうです、少し短いですね。
Q:次にお作りになる作品もきっと大作だと思うのですが、またインターナショナル版と両方できる可能性がありますね。
監督:まあ、その時にならないとわかりませんが、今度はどの人にも同じヴァージョンを見てもらえるようにできたら、と思っています。まだ、次のプロジェクトは始まったばかりですけどね。
Q:最後にもう一つだけ。『~伝説誕生』でスディープが登場したので、きっと『~王の凱旋』でも出てくるのでは、と我々は期待していたんですが。
監督:(ちょっと苦笑いしつつ)そうなんですよ、出てもらいたい気持ちはあったんですが、ちょうどいい場面がなくて、おまけに全編がとても長くなってしまったので、あきらめました。スディープに登場してもらうには、それなりの素晴らしいシーンがないとダメですよね、単なるカメオではなくて。だから実現しなかったのです。
Q:お疲れのところ、本当にありがとうございました!
![]()
©TWIN
本当に些末な質問に、丁寧に答えていただきありがとうございました、ラージャマウリ監督。明日はチネチッタ川崎での絶叫上映ですね。皆さん、どうぞたっぷりと楽しんで下さい。そうそう、本日<完全版>の予告編もアップされました。
「バーフバリ 王の凱旋<完全版>」予告編
6月1日(金)まで、指折り数えて待ちましょうね!